はじめに
AIを活用して「業務を効率化しよう!」「事務作業が楽になりそう!」と思って始めてみたものの、使いこなせず、結局そのままにしていませんか?
- 「プロンプト(AIへの指示)を完璧にしないと、正確な回答が出ないのではないか?」
- 「AIが出した回答が、物足りない」
- 「どのツールを使えばいいかわからず調べたり試したりするのが大変」
これは、AIを使い始めたばかりの多くの人が感じている悩みかもしれません。AIが広く認知され様々なツールやノウハウで溢れていますが、結局思っていたほど身近な事務仕事に活かせていない人が多いのが現状です。

本記事では、この問題を解決し、AIを「仕事のパートナー」に変えるための、具体的なマインドセットと実践方法をご紹介します。
当ブログは現役大学職員の私が、AIツール(Gemini, ChatGPTなど)を活用し、大学事務の業務改善をするためのAI活用ブログです。私自身、文系大学卒の非エンジニアの事務職員なので、専門用語は避けて読者の皆さんが分かりやすく、すぐ使える情報をお届けできるよう心がけています。
プロフィールの詳細は、以下をご覧ください。
「最初から完璧」を求めてしまう
大学職員の業務特性: 大学の業務は、正確性が求められる仕事や個人情報の管理がとにかく多い。特に公的な文書や対外的な発信にミスは許されないため、無意識のうちにミスのない「100点」を目指す習慣がついている。
AIへの過度な期待: AIに対する期待値がどんどん高くなり、「使えば一瞬で完璧な成果が出るはず」と期待しすぎる。
AIとの向き合い方: AIが作成したものでも、最終チェックと提出の責任は自分にあるため、結局直すなら最初から自分がやればいいのでは?と思ってしまう。
完璧主義を捨て「70点スタート思考」へ転換する
AIの役割を再定義する:「完成品」ではなく「たたき台」
AIの強みは、ゼロからイチを最短で作り出すこと。
AIは「優秀な新人スタッフ」であり、あくまでベースを作成する担当です。あなたが時間をかけるほどでもない単純な作業を最短で仕上げてもらい、あなたはあなたにしかできない状況や求められていることを踏まえて、創造性や工夫が必要な作業に時間を費やせるようにするというイメージを持ちましょう。
「ドラフト作成」と「校正・磨き上げ」に作業を分ける
AI(70点): 構成案、情報の要約、初稿作成など、「手を動かす」作業を一気にAIに任せる。
あなた(+20点): AIの成果を基に、表現の微調整、専門用語への修正、独自の文脈の追加、最終的な責任あるチェックを行う。
【実践例】会議の議事録作成の場合
❌ 完璧主義の罠
完璧な要約文をプロンプト一発で要求しようとして、プロンプト作成に時間をかける。
✅ 70点スタート思考
まずはAIに「議事録の素案」を箇条書きで出力させ、それを自分の言葉で肉付け・調整する。
具体的な心理的ハードルの下げ方(スモールスタート)
小さな「雑な成功体験」を積み重ねる
ステップ1: 業務に関係ない「趣味」や「プライベート」のメール作成をAIに任せてみる。(失敗しても誰にも迷惑がかからない領域で慣れる。)
ステップ2: 「ミスしても問題ない」レベルの業務(例:自分用のメモの要約、使わなかったExcel関数の確認)にAIを使ってみる。
ステップ3: 「締め切りまで余裕がある」タスクで、あえてAIの成果をメインに使ってみる。



プロンプトは「箇条書きのメモ」から始める
最初から長文の完璧なプロンプトを作ろうとしない。「〜について、3つのポイントで説明して。」など、単語レベルで指示を出して、まずはAIの反応速度を体験する。
失敗を恐れないマインドセット
AI活用における失敗とは、「思った通りの回答が得られないこと」です。それはあなたの失敗ではなく、AIへの指示が不十分だったという「今後の課題」だと捉えましょう。何度も繰り返し質問をしたり、色々なシチュエーションで使ってみたりすることでプロンプト(AIへの指示)のコツが分かってきます。
まとめ:完璧は求めず、とりあえず聞くの繰り返し
完璧は求めず、AIを「たたき台」として活用することで、あなたは「あなたにしかできないことにより時間を費やす」という、より高度で重要な役割に集中できるようになります。
現状のタスクではAIを使う必要がなくても、今後より単純かつ時間のかかる(あなたがやるほどでもない内容の)作業が回ってきた時にAIを使えるようになっておくと、本当に楽になります。
まずはAIに聞いてみて、どんな指示をすれば求めている答えが返ってくるのか、どんなことが得意でどんなことが苦手なのか。特徴を掴んでいくことがAIを活用できるようになるための最もシンプルなステップです。





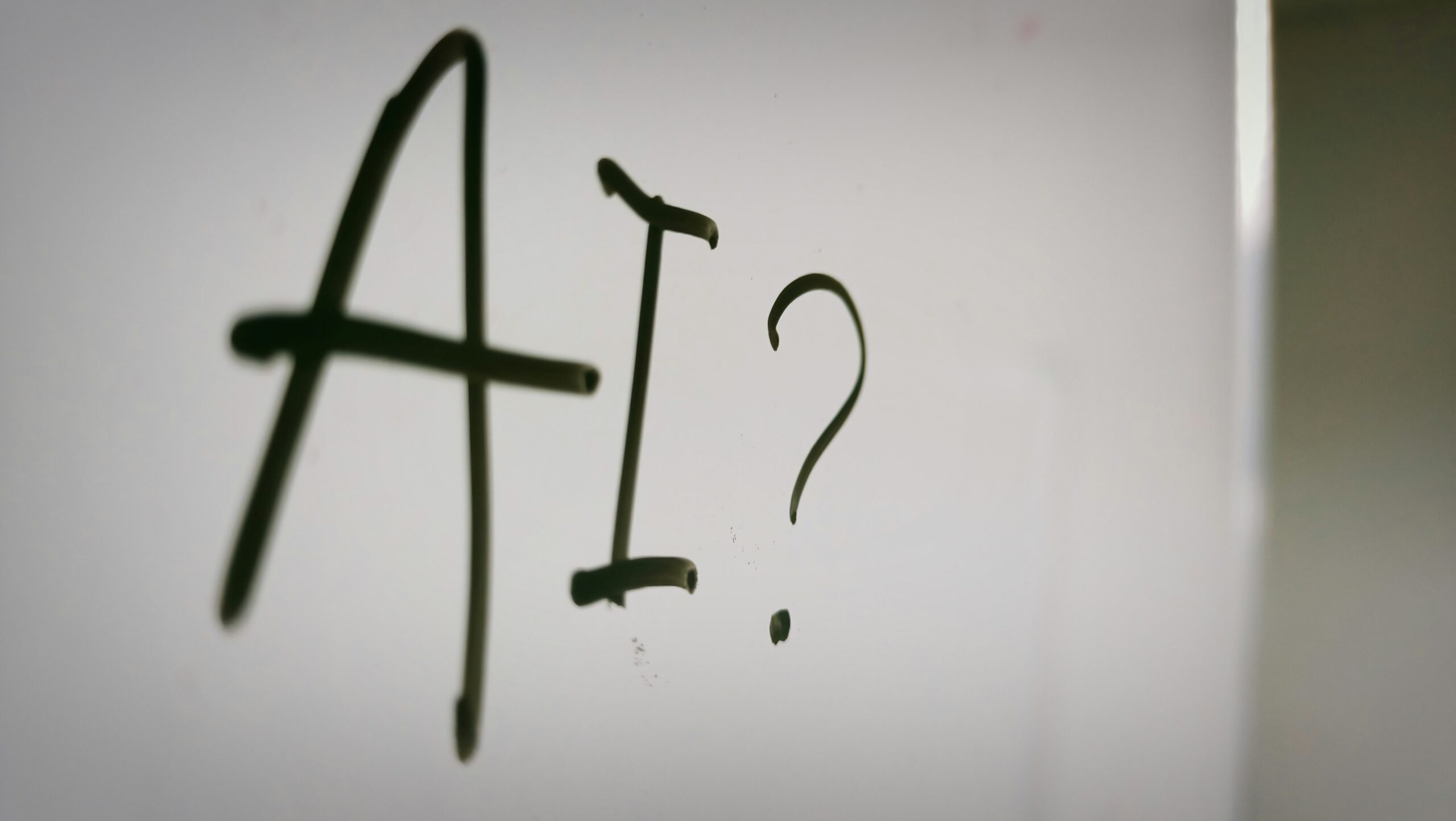






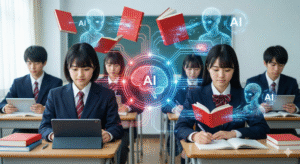


コメント