はじめに
本格的に大学入試の時期となり、総合型選抜やが学校推薦型選抜でほぼ必ず必要になるエントリーシートや自己推薦書、志望理由書などの出願書類。「何を書けばいいか分からない…」「もっと上手い文章にしたい!」「より評価される文章を書きたい。」と悩んでいる受験生の方も多いはず。そんな時、ChatGPTのようなAI(人工知能)に「代わりに書いてもらおう」と考えたことはありませんか?
でも、一番の心配は「大学側にバレるんじゃないの?バレたら評価が下がってしまうのではないか?」ということ。
この記事では、出願書類でのAI利用について、現役で都内総合大学の入試課で働いている大学職員視点で「ぶっちゃけどうなのか」を徹底解説していきます。




当ブログは現役大学職員の私が、AIツール(Gemini, ChatGPTなど)を活用し、大学事務の業務改善をするためのAI活用ブログです。私自身、文系大学卒の非エンジニアの事務職員なので、専門用語は避けて読者の皆さんが分かりやすく、すぐ使える情報をお届けできるよう心がけています。
プロフィールの詳細は、以下をご覧ください。
「AI丸投げ」はバレる可能性大!
まず結論から。ChatGPTなどに丸ごと文章を作らせた場合、それがAIによるものだとバレる可能性は非常に高いです。
「でも、どこかのサイトから文章をコピペしている訳じゃないしバレないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、判定する側が見ているのは「コピペかどうか」だけではありません。
なぜAIだとバレるのか? 3つの落とし穴
大学の教授や入試担当者は、毎年、数百から数千通の出願書類を読んでいます。これだけ多くの書類を確認していると、100%AIに書かせた文章の「違和感」を見つけるのは難しいことではありません。
AI特有の「クセ」と「具体性のなさ」
AIが生成する文章には、特有の「クセ」があります。
- 一見すると完璧で、論理的すぎる。
- 「~することが重要です」「~と言えるでしょう」といった、当たり障りのない表現が多い。
- 感情や言葉の言い回しなど、文章に高校生らしさが感じられない。
何より、AIはあなたの「具体的なエピソード」を知りません。
「部活動で困難を乗り越えた」「文化祭で仲間と対立した」といったあなたの経験に基づかない文章は「中身がない」と判断されてしまいます。
大学側が「AI検出ツール」を使い始めている
海外の一部大学ではすでに、Turnitin(ターンイットイン)のような剽窃(盗作)チェックツールに「AI検出機能」が搭載されています。日本の大学でも、こうしたツールを導入する動きは進んでいます。
Turnitinとは、提出されたレポートなどの剽窃(盗作)チェックを 行うツール。 インターネットに載っているWebページや文献のほか、 同じ課題に提出された他のレポートなどとも比較し、 どの程度コピー&ペーストされた文章があるかを判定する。
これらのツールは完璧ではありませんが、「この文章はAIによって書かれた可能性がXX%です」とアラートを出すことができます。疑いを持たれること自体が、すでにもうマイナスですよね。
面接や他の審査でボロが出る
これが一番の「落とし穴」です。
書類選考を無事に通過したとしても、次に待っているのは「面接」です。面接官は、あなたが提出した出願書類を元に質問をします。
・ここに『貴学の〇〇という点に強く惹かれた』と書いてありますが、具体的にどういう部分ですか?
・この経験から『リーダーシップを学んだ』とありますが、一番大変だったのはどんな時でしたか?
AIに書かせた文章では、この「なぜ?」「具体的には?」という深掘りに答えられません。自分の言葉で悩み、考え抜いて書いた文章でなければ、面接官の鋭い質問には答えることができません。






AIは使うな!…ではなく「賢く」使おう!
AIに「丸ごと代筆」させるのはNGです。しかし、あなたの文章作成を「手伝ってもらう」のは非常に有効です。ここからは出願書類の作成におすすめの「賢いAI活用術」を紹介していきます。
活用法① アイデアの「壁打ち」相手にする
何を書けばいいか分からない時、AIは最高の相談相手になります。
【プロンプト例】
大学の志望理由書で、高校時代の生徒会活動のアピール方法を5つ提案してください。
看護師になりたいという動機を、深掘りするための質問を10個作ってください。
AIが出してきたアイデアを見て、さらに自分の思いを言語化してもらったり考えを深めたりするキッカケにしましょう。
活用法② 構成(アウトライン)の「たたき台」を作ってもらう
いきなり文章を書き始めるのは大変ですよね。まずは構成を決めていきましょう。
【プロンプト例】
志望理由書(800字)の構成案をください。以下の要素を含めてください。
・結論(なぜ志望するか)
・具体的なエピソード(高校時代の経験)
・大学で学びたいこと
・将来の展望
AIが作った構成案を元に、「このエピソードはもっと具体的に書こう」「ここは順番を入れ替えよう」と自分流にアレンジするだけで、格段に書きやすくなります。
活用法③ 自分が書いた文章を「添削」してもらう
これが最も安全で、効果的な使い方です。文章の80〜90%は必ず自分で書くことをオススメします。その上で、最後の仕上げをAIに手伝ってもらいます。
【プロンプト例】
・以下の文章を、もっと読みやすく、説得力のある表現に修正してください。ただし、元のエピソードや熱意は変えないでください。(←ここに自分の文章をコピペ)
・以下の文章に、誤字脱字や文法的な間違いがないかチェックしてください。
AIは誤字を見つけたり、もっと適切な言葉遣いを提案したりするのが得意です。自分の「想い」はそのままに、文章の「質」だけを高めることができます。
出願書類を作成する際にオススメのAIツール
私が出願書類を作成する際に、最もオススメのAIツールはGoogleの「Notebook LM」です。
Notebook LMは、一言でいうと「あなたがアップロードした資料だけを情報源にする、あなた専用のAIアシスタント」です。
一般的なチャットAIがインターネット上の膨大な情報から回答を生成するのに対し、Notebook LMはあなたが指定したPDFやテキスト、ウェブサイトの内容だけを完璧に理解し、その範囲内で質問に答えたり、要約を作成したりします。
そのため、志望先の大学の公式サイトや大学でもらった資料の電子データなど指定した資料から情報を得ることができ、意図しない情報が混ざってしまう心配が少なく、信頼性が非常に高いのが最大の特徴です。Googleの最新AIモデル「Gemini」を搭載しており、非常に高い精度を誇ります。
以下に使い方や詳しい特徴を紹介しているので、参考にしてください。
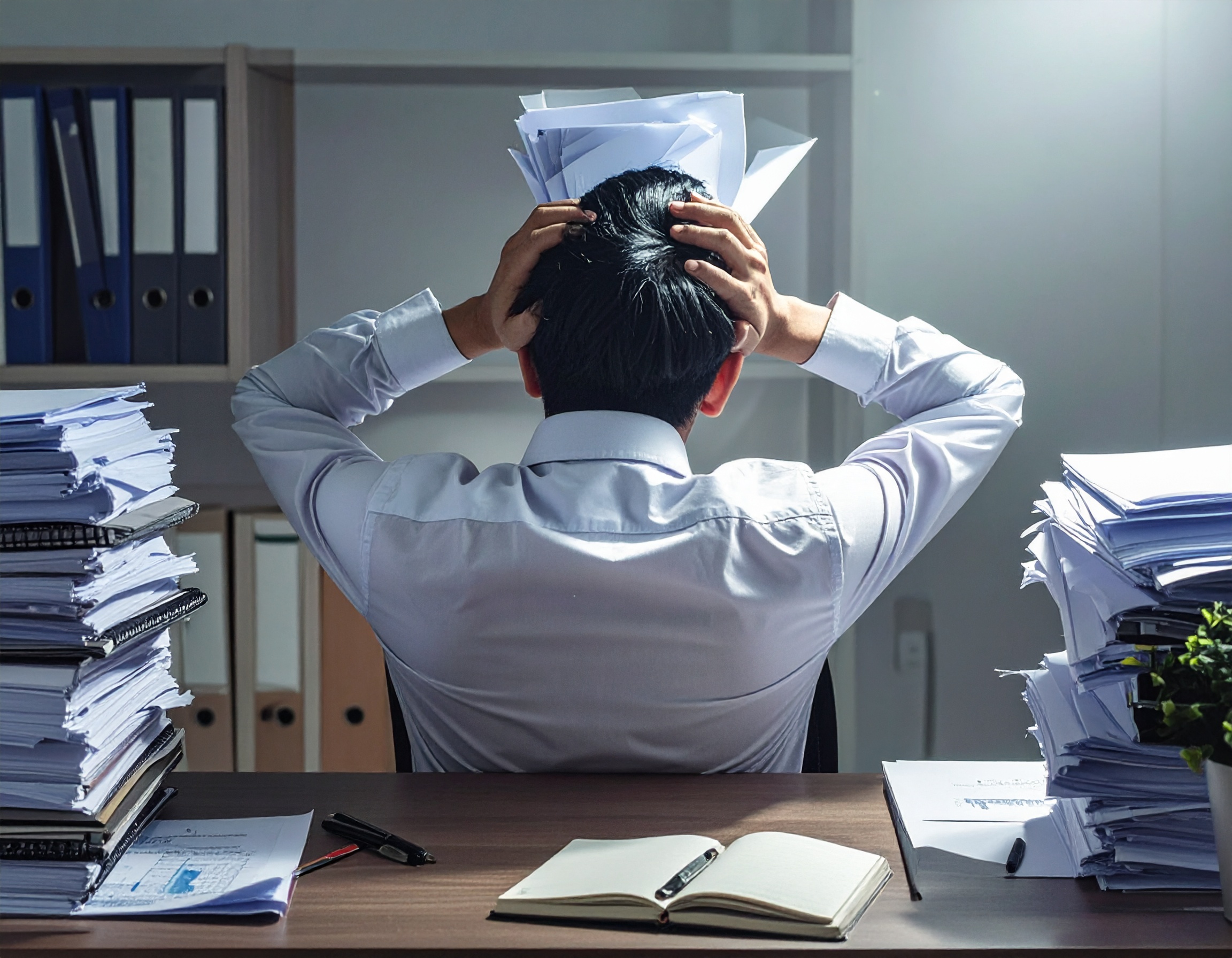
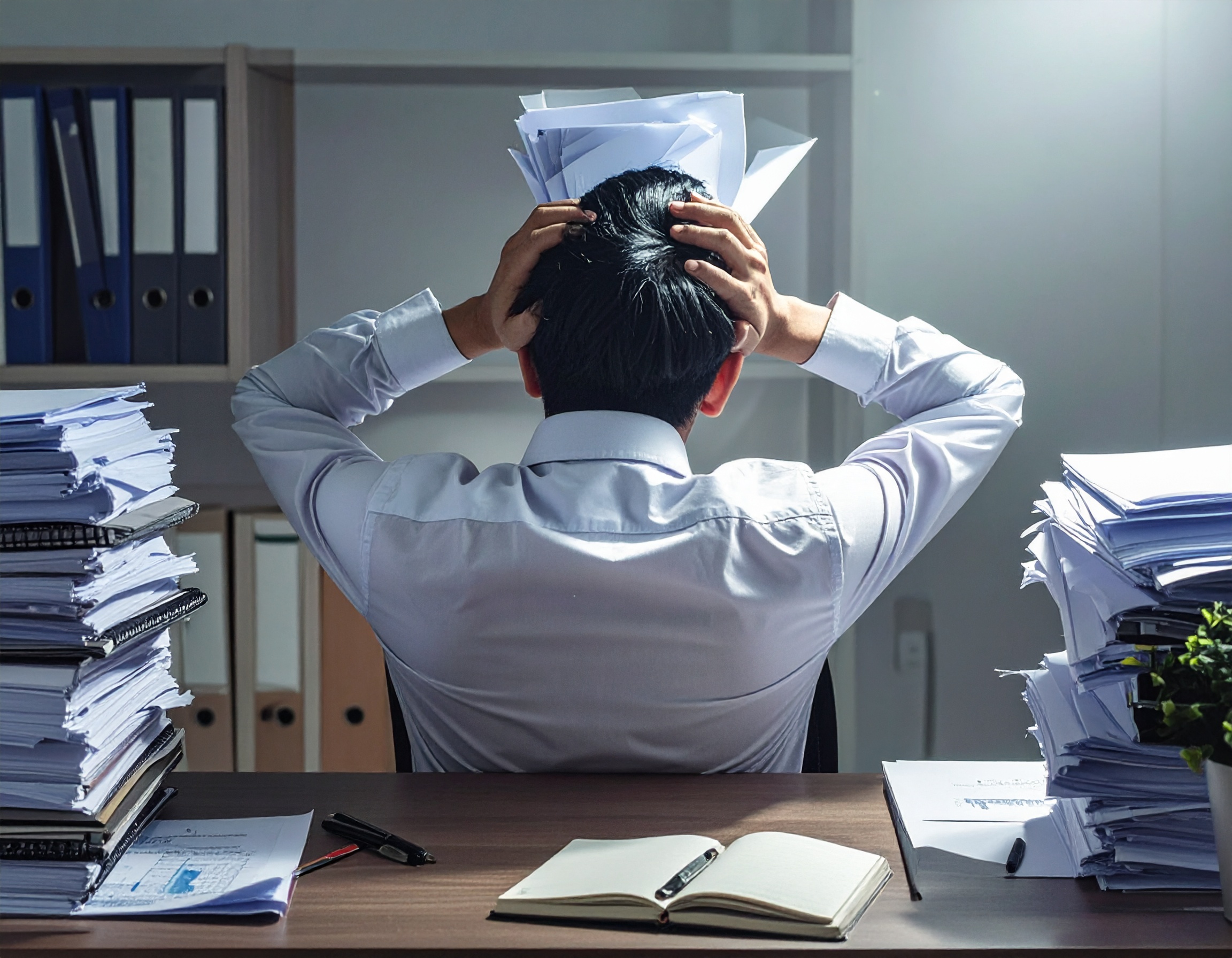
まとめ
大学入試(特に総合型選抜や学校推薦型選抜)は、あなたが「どんな人間で」「どれだけの熱意を持っているか」が非常に重要視される入試形態です。そこを完全にAIに任せてしまっては、一番大切な部分が伝わりません。
AIを賢く使いこなし、あなたの魅力を最大限に詰め込んだ出願書類を完成させてください。応援しています!












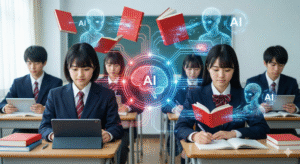


コメント