はじめに
このブログでは、大学職員の現場目線で AIを使った業務効率化の具体的手法 を紹介します。専門知識がなくても実務にすぐ使える内容を中心に、実例・プロンプト・Excel関数などの“使えるネタ”を提供します。
なぜ私がAIに取り組むのか
数年にわたり、次のような非効率に直面してきました:
- 前任者が作成したマクロが修正できず、そのまま手作業で対応していた。
- 学科ごとに異なるデータ形式で資料提出を求められ、都度ExcelやAccessで整形していた。
- 志願者データの集計や分析に時間がかかり、外部システムを導入しても十分に活用できなかった。
少子化の煽りを受け、少ない人員でやるべき仕事は増える一方です。この現状を放置せず、現場レベルで改善できる手段としてAIを試しました。
今回の記事で紹介するAI活用法
専門知識がなくてもすぐに試せるAI活用法を3つ紹介します。どれも実務で役立ち、導入コストは低めです。
1. AIでビジネスメール文面を自動生成
教員や外部業者宛の丁寧なメール作成はAIの得意分野です。要点を箇条書きにするだけで、適切なビジネスメールに整形してくれます。
プロンプト例(コピペして試してください)
以下の要点を盛り込み、△△学科〇〇先生への丁寧なメールを作成してください。 ・オープンキャンパスの件で相談 ・来週月曜か火曜の午後で30分ほど時間を確保してほしい ・候補日時の提示を依頼使い方のコツ
- 件名を明記する(例:「オープンキャンパスについての相談」)。
- 相手の立場に応じた敬語レベルを指定すると精度が上がる。
- 返信期限や必要資料の有無など、要点を細かく伝える。
2. AIによるPDF資料やWebサイトの要約
会議資料(PDF)や参考情報のWebページを渡して「要約して」「重要なポイントを3つ教えて」「表にして」と指示すると、情報収集が短時間で終わります。
プロンプト例(コピペして試してください)
以下のPDF資料の概要を300字以内で要約してください。特に、この研修で得られる具体的なスキルと、対象者を明確にしてください。 [ここにPDF資料のURLを貼り付ける、またはPDFの内容を直接貼り付ける]※PDFの内容を直接貼り付けたり、長いWebページのURLを指示することも可能です。
実務での使いどころ
- 会議前の事前確認資料作成
- 外部研修の内容整理
- 複数資料の比較表作成(例:業者A・業者Bの機能比較)
注意点
- 元資料の機密性や取り扱いに注意する(学内規程に従う)。
- AIが抽出する要点は過不足があることがあるため、最終チェックは人が行う。
3. AIでExcel関数を自動生成
「〇〇学科のデータだけを抽出したい」など日本語で目的を伝えると、そのまま使える関数を提示してくれます。自分のデータ構造(A列が学生番号、B列が学科など)を伝えると、コピペで使える関数が得られます。
プロンプト例(コピペして試してください)
以下のExcelデータについて、指定された条件でデータを抽出・集計する関数を教えてください。 【データ構造】 ・A列:学生番号 ・B列:学科名(例: 文学部、経済学部、法学部) ・C列:学年 ・D列:志願者区分(例: 一般入試、推薦入試、AO入試) ・E列:合否(例: 合格、不合格) 【目的】 ・「文学部」かつ「一般入試」で「合格」した学生の数を数える関数(セル参照はB列, D列, E列を使用)を、F2セルに設定できるように作成してください。※あなたの実際のデータ構造に合わせてプロンプトを調整してください。
実用例
- フィルタやIFS、VLOOKUP、COUNTIFS、SUMIFSなどの関数を具体的なセル参照付きで生成。
- 複雑な条件付き抽出や、ピボット不要の集計式も相談可能。
導入の利点
- 関数の調査時間が減る
- 手入力によるミスが減る
- テンプレート化がしやすくなる
ケーススタディ(実例)
事例A:オープンキャンパスの連絡業務
- プロンプトを使ってメールをテンプレ化 → 1通あたりの作成時間が従来の半分以下に。
事例B:学科別データの整形
- Excel関数(抽出+集計)をAIに生成させ、調査回答用のデータ作成時間が短縮。
※数値は環境により異なりますが、実務で効果を確認できた例として紹介します。
AI導入時の注意点
- データの取り扱い:個人情報や機密データは学内規程に従って扱う。外部にアップロードする前に必ず確認すること。
- 最終チェックの重要性:AIは誤情報を生成することがあるため、最終判断は人間が行う。
- 学内文化への配慮:定型化が進むとコミュニケーションが機械的になりがち。相手や状況に応じて調整すること。
まとめ
大学の事務には、慣習や前例踏襲が残る部分が多く、非効率な作業が蓄積しています。AIはそれらの定型作業を効率化し、職員が企画や学生支援といった価値の高い業務に時間を割けるようにするためのツールです。
このブログでは、現場で使える実践的な手法を継続して発信します。この記事が、あなたの業務改善の第一歩になれば幸いです。












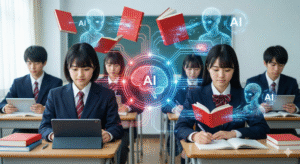


コメント